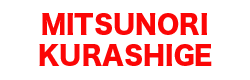■TAKASHI KIKUI's Article / 菊井崇史氏の評論文を読む

■ 発光体(前部) 2002年 2003年 244x244x610cm. 鉄、蛍光灯 C・スクエア/神奈川県民ホールギャラリー
光を生きる光、ふれる鬩ぎあいを射して
■ 菊井崇史
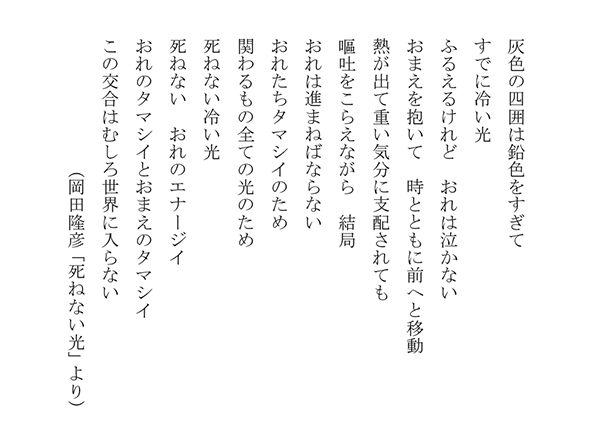
邂逅は言葉に由り、もたらされた。言葉を生きる責務にも似た想いに、互いの生存の位置が確認されたのだった。海の気配が靡くトラックヤードの一角、元は倉庫だったときくアトリエを訪ね、出逢い、聲をかわし、咄嗟に、倉重光則の制作行為、事物を光を摑むその掌が、言葉をこそ生きている、言葉自体の闘争でもあるのだと覚えた。倉重光則は絶えず、自身の言葉を揺るがし、攻撃し、新たな言葉のすがたに手を伸ばす。腕が捥げてもかまわない、そんな気迫が会話のふしぶしに宿っていた。倉重光則の営為にまきこまれ生じる実景は、われわれの言葉に届く。言葉を迫る、そう信じた。もう、三年程が経った。その間、幾度か耳にした、自分を作家だとかアーティストだとはおもっていないという倉重光則の聲に、わたしは心底、共鳴し、同意した。その理由は、生存、その一語に収斂するだろう。生存の位置に。わたしたちは地を、地べたを生きたいのだ。地を破り、地下を埋もれ、地を全身でいだくように、叶うならばいだかれるように、地べたに這い蹲りたいのだ。現在の耐えるべきを耐え、生きるべきを生きるために。だからこそ、生存を全身で賭して、あるべき言葉の具体を求め、要請する。倉重光則の制作する具体と、そこに刻みこまれある行為から、いかに言葉を惹き起こすのか、綴るのか、衝突させるのか、その応答はきっと、倉重光則との邂逅の時に生じた約束なのだ。護りたい。
開始の瞬間があった。光が晒された。倉重光則が呈示する制作に、蛍光灯を主要として備えるにいたった理由は、幾度か自身によって言明されている。二十歳を幾らか過ぎた倉重は、自らの描いていた絵画が光の照らされ方でその表情をかえることを蛍光灯で試し、おそらくは不意に、握られた光を身辺の新聞紙に置いた。それが、決定機となった。蛍光灯の光に、新聞紙の文字が消失して見えた。光に白み、印字が掻き消された紙上を瞳はうつし、その刹那を摑んだ。一九六八年だった。一九七〇年を前後し発表され、「物質主義的エクスタジーmaterialisim Ecstasy」と名づけれてた一連は、蝋に埋められた蛍光灯のすがた、セメントから成る立方体の底辺を蔽い囲む蛍光灯のすがたを露にし、光で見せるのではなく、光を見せるという局面を体現する。以後、光を見せる実践を途絶えることなくはたしつづけた倉重光則の四十幾年は、一九六八年におとづれた経験、その亀裂から遠ざかり、乖離するのではなく、裂け目を現在にかかえこみつづけながら生きてきたことの証左だ。そこには絶対的な理由があったはずなのだ。一九六八年という日付が刻みこまれていたであろう新聞紙の文字が、蛍光灯に密接したがゆえに、絵を見せるための光によって見えなくなるという事態は、光で見せるのではなく、光を見せるという方途を倉重に告げ、その刹那、蛍光灯の光に掻き消えたのは、紙上の文字だけではないことは明白だ。文字を照らし消した光は、倉重自身の神経を巡り、身体を組織、構成する言葉をも眩しく、襲ったのだ。光に開放されものは何だったのか、その光に封印されたものは、光の拡がりは何を尽くし、届けたのか。幾多の出来事が、倉重が光を摑んだその刹那に生起したのだろう。同刻、一九六八年現在までに経験された幾多の出来事に対する応答の術を開示されもしただろう。光による言葉への闘争の顕現にうつりもしただろう。光に埋められ、生じた空白から、あるべき言葉を要請する意志の具体的な光景だっただろう。その実景は現在という実景に繋留されているのだ。わたしは、倉重が摑み、倉重を摑んだ出来事に籠められた真意を深く、しりたい。光でから、光をへいたらざるをえない、その選択に、確かな生存の切実、痛切を覚え、想うから。
光の実際を配備することにひらかれた制作行為の初動が、六八年から七〇年代のはじまりである事実は重く、倉重光則とわたしの邂逅、繋がりの在りかを知らしめておもえる。六〇年代中葉から七〇年代初頭に確乎と顕在し、命懸けではたされたであろう行為の具体を見、知り、覚えたという経験は、わたしが詩を書記し、写真を撮り、生きる覚悟を定めた理由の揺らぐことのない一端となっているからだ。より厳密に言えば、多くは六〇年代に書かれた詩の集成であり、それぞれ一九七〇年二月、七一年六月に発刊された『現代詩文庫岡田隆彦詩集』、『現代詩文庫吉増剛造詩集』の二冊を手にしたことが、わたしにとり言葉を生きる契機のひとつとなり、その流れの必然に、岡田隆彦が同人のひとりとして発足された一九六八年創刊の写真同人誌『PROVOKE』と、その同人、火種であった中平卓馬の同誌の終刊後一九七〇年十一月刊行の写真集『来たるべき言葉のために』および、それらの発現が原動を担い、徹底的に言葉に関与する写真、映像の実践を開始し持続する吉増剛造の営為との邂逅が、わたしが写真を撮る意識的な選択の理由となっているということだ。ここに記した固有名が、特別の意味をもつことを隠すつもりはない。わたしがこれらの多くと邂逅したのは、二十代の前半、二〇〇〇年代の幾年を過ぎていたが、戦後現代詩そして写真史の亀裂、切断たりえたその実際と具体に、いかなる意志を見出し、引き受け、継ぐべきを継ぐことができるのかという想いなしには、詩を写真を開始することはできなかった。当時に生じた亀裂は、明かな切実として、奔り届いていたのだった。それは、徹底的に、生存の言葉の姿勢の問題だ。『言葉を生きる』と題され、その名を主題された書物で岡田隆彦は、「言語が肉体と相似の、複合した影像でありうるとすれば、言語による表現もまた一つの肉体であっていい。いや、行為であっていいのだし、生きること自体であるべきだ。とりわけ、生きているからこそ変質もあり得るし死も抱きかかえているところの言語による、きわめて緊張した、ヴィヴィッドな表現としての詩は、現実社会には意味がないということだ。生命の韻律と脈絡とそして内容が不分明ながら自身を衝迫する意思をそのままの形で、肉体がさまざまの異質な器官を組織してなっているように、組織し具体化することはもちろん易しいことではないにしても、その努力は必要だろう。その努力および工夫をもって、詩は存在ぜんたいに力を及ぼすことができるのだ。(「生ける現在」傍点引用者)」と言述し、この一文の初出は、二年たらずで活動を終える『PROVOKE』の有終として一九七〇年三月に発刊された『まずたしからしさの世界をすてろ』だった。中平卓馬は、一九七三年刊行の『なぜ、植物図鑑か』において、「われわれを支えていたのは運動としての展望よりも、当時支配的であった写真とそのメディアではできないものをやりたいという極めてプリミティブな衝動であったように思える。だからわれわれの間には必ずしも共通した問題意識があったわけではない。(「記録という幻影」)」と『PROVOKE』を述懐しているが、しかし、先の岡田隆彦の文に貫かれる「言葉を生きる」という信念は、中平においては、写真で生きるのではなく、写真を生きること、写真を「生きること自体」とする意志、覚悟、自覚であり、紛れもなく「プリミティブな衝動」を先行するかたちで、その実行の根拠となり、中軸として支えていたはずのものだ。すくなくとも、岡田、中平にあってはつよく、その事態が確認できる。そう、受けとったし、それを受けとった。そこに見出される意志が、二〇一〇年代の現在を生きた時いかに息吹き、鼓動し、いかなる連繋を見出し、何に衝迫するのかを問い、同時にこの意志に対し、律され、応答することができるのかを問いただされることが、詩と写真の開始に刻印されているのだ。この事実は、わたしが倉重光則という存在、営為を思考する際、決して無縁ではありえない。光で見せるのではなく、光を見せることを意志し、徹底的に事物、光と対峙しながら絶えず言葉を希求する倉重の営為に確かな通底を覚えるからだ。
一九七四年、田村画廊での展覧会に生じ、巡らされた出来事は、光を見せる局面を開示した時と共に、倉重光則の営為の軸の実景をつぶさに伝達するとおもえる。展覧会に、倉重は、画廊の壁にガムテープで三〇センチ四方の枠を貼り、かたどった。正方形、ガムテープの枠内を倉重は、掌で直にふれ、こすった。それはおよそ開廊の時間、午前十時頃だった。それから閉廊の午後七時頃までの八時間、裸の掌を、ひたすらに壁にこすりつづけたのだ。摩擦に、熱は生じつづけた。汗が滲み湧く。垢もこすれる。皮膚はいたみ、肉刺のようなものができた。汁が出る。それでもやめなかった。いや、だからこそ、やめなかっただろう。擦過をこえて、さらに。八時間だ。田村画廊の主催だった山岸信郎と美術評論家の宮川淳がその内の幾時間を倉重の傍で過ごした。見守る、その言葉がとても適切だとおもう。午後七時、倉重はこする掌をとめ、ガムテープを剥がした。そこには、周囲の壁の色とは異なる正方形が生じていた。宮川淳は、その日はじめて顔をあわせ、聲を交わす倉重に、これしかない、という感想を告げた。この一連を倉重は、そう述懐する。忘れられない出来事、自身にとっての画期だと。倉重本人でなくとも、この話に伝わる光景は誰も、忘れられないだろう。忘れてはならない。慄えるような光景だ。常軌を逸した行為と持続の時間だ。烈しく、心をうたれる。あまりに切実で誠実な行為と持続の時間だ。わたしには、このひと時にはたされた行為と時間が、おおよそ倉重光則の生涯に持続されつづく実際としてうつる。だから、一九七四年、田村画廊での八時間の出来事は、その限定性と特殊性を破るだろうし、ここに今、人間が通過し、経験し、確かめ直さなければならない行為と時間が集約されているのではないか、そんな予感を覚える。「紙の上にインクのしみをにじませてゆくという,ただそれだけといえばそれだけの行為,だがそれが未知の空間を開けたら……」宮川淳は、『現代詩文庫岡田隆彦詩集』の裏表紙に、願いに似た想いを寄せている。この言葉に、倉重光則のすがたが襲なるのは言うまでもない。わたしは、その場に立ち会ってはいない。正方形も、肉眼では見ていない。きいただけだ、だけれど、はっきりとわかる。画廊の壁に定着した三〇センチ四方の正方形の色ならぬ色、熱ならぬ熱は、われわれが奪還しなければならない必需としての「未知の空間」を垣間見せたはずだ。確乎たる物理として。そして、光や事物との渾身の関係の直中でひかられる「未知の空間」の逐一を束ね、自らの生成されつづく拠点とし、言葉を揺さぶり、攻撃し、新たな言葉のすがたを要請することが、倉重光則の手放さない倫理なのだ。
「映像はそれ自体としては思想ではない.観念のような全体性をもちえず,言葉のように可換的な記号でもない.しかし,その非可逆的な物質性―カメラによって切りとられた現実―は言葉にとっては裏側の世界にあり,それ故に時に言葉や観念の世界を触発する.その時,言葉は,固定され概念となったみずからをのり越え,新しい言葉,つまりは新しい思想に変身する.」と『PROVOKE』は、創刊号に宣言し、闘争を開始した。憤慨させる、刺激する、挑発する、引き起こす等の意味をもつ語としてPROVOKEを冠し、〈思想のための挑発的資料〉というサブタイトルを付した彼らの意志とその実践には、いささかの齟齬もない。「当時われわれを支えていたのは、それまで支配的であり、今もなおそうである、意味にべったりとへばりつき、意味から出発し、意味に還る既成の言葉のイラストレイションとしての写真の否定する衝動であった。映像はけっして言語とは無縁ではありえない。いやむしろ言語のレベルにまといつき、それを時として挑発し増殖することができるにすぎない。「思想のための挑発的資料」というのはむしろ「言葉のための挑発的資料」と言い換えた方がいい。(「記録という幻影」)」と中平は終刊後数年も経たない内に『PROVOKE』の感懐を記し、さらに二十年程の時を経た岡田隆彦は、中平卓馬が東松照明との関係で、六八年に開催される日本写真協会の「写真100年展」の準備作業にかかわりながら「写真の歴史の再構成の作業だったにもかかわらず、写真史の近い過去をいったん切り落として、もう一度自分の写真の歴史を作ろうと、まるで明治のはじめの若者みたいに、ロマンティックに、ヒロイックに興奮していましたね。(「無政府状態で生まれた異種交配」『デジャ=ヴュ十四号』)」と当時を思い出す。「既成の写真アカデミズム、あるいは報道写真ジャーナリズムに一石を投じ」るため、自身は言葉でそれに加担したのだと。中平、岡田の回顧、把握はおおよそ一致し、写真から言葉への、言葉そのものを渦中とする闘争、変革の要請だった『PROVOKE』創刊の宣言にふたたび漸近する。彼らの目論見は、いかなる「映像」、写真意匠の提示によってはたされ、いかなる認識、批評、詩の言葉を体現したのか、そしてその変遷自体が見せる軌跡は、現在を巡り、問う。
「《PROVOKE》のめざしたものは、写真家の肉声(パロール)の獲得ということであった。それは既存する美学や価値観による制度的に整序された視覚(ラング)に対する肉声による切込みであったはずだ。(「記録という幻影」)」と中平は記す。「肉声」とは、「ただそこに在ることによって、あるいはただ発せられることによってそれだけで人を震撼させる狂気に満ちた孤立した「物体」のような言葉。それは他者とのコミュニケイションを前提した、連続的な、開かれた言葉ではあり得ない。そしてこのような「炸裂する言葉」は、ここに、今一人の人間によって苛烈に生きられた言葉なのである。(「写真は言葉を挑発しえたか」傍点引用者)」と言明される「言葉」であり、「肉声」を写真が具体するならば、「カメラを取り、ファインダーをのぞく時、シャッターにかけた指先にはこの生の暗闇の総体がおしかぶさっている(「同時代的であるとは何か?」『来たるべき言葉のために』)」と告げられる「生の暗闇の総体」、つまりは、個々の生のはかりがたき重さを託されうる全身、全面を意匠しなければならない。世界の現前、全体に均衡し、匹敵し、つりあう言葉、写真としてではない。土壌がちがう。個々の生を見定め開示する視座の決定的な露出の必要を訴えたのだ。その方途に、中平は、当時、アレ・ブレを選択した。アレ・ブレに「生の暗闇の総体」を見極めた。『PROVOKE』、『来たるべき言葉のために』の中平卓馬の写真は、倉重が光で絵画を見せるのではなく、光を見せると選択したことと同様、ハイコントラストに焼かれ、光に潰された写真、もしくは闇のひしめく写真を現在させ、撮影された対象だけでなく一層、光と事物を同律の一面として晒す一葉一葉の写真自体を呈示したと言っていい。「制度的に整序された視ラング覚」、逆に言えば「視ラング覚」を「整序」する「制度」に抗するための「肉声」、その具体形式であることがアレ・ブレの真意だった。しかし、「肉声による切込み」は、彼の思いどおりには成就しなかった。「肉声などは一瞬の後に制度的な視覚のうちにのみこまれてしまったに違いないのだ。むしろ《PROVOKE》を通じて得たたった一つのものは、この時代の難攻不落の多重層構造の発見であったかもしれないのだ。(「記録という幻影」)」と。決死に見定められた形式から内実が、「肉声」が、「生の暗闇の総体」が抜きとられ、剥ぎ取られ、形式だけが制度化され、ファッションとなりはて、体制に組みこまれたのだ。以降の中平卓馬は、この屈辱的な実感をもよおした経験の実際がゆえに、その直後から自作とその方法への厳しい検証をはじめ、アレ・ブレという形式を否定し、ひたすら「事物の存在」そのものをとらえる視座の獲得をめざす。「眼はすでに制度化された意味をひきずったまま、意味の確認をしか世界に求めようとしない。眼は外界へ通じる透明な窓ではなく、世界から私を遮断するシェルターに変わる。世界は私の逆送された投影である。/けんらんたる白日の下の事物の存在。事物からあらゆる陰影を拭い去ること。光あれ!この陰影こそ〈人間〉の逃れ去る最後の堡塁である。」「一体われわれが〈詩〉と呼び慣わしているものとは何なのか? それはひょっとして、世界と私とをつなぐ〈イメージ〉と同義なのではないだろうか?」「だが投書者が〈詩〉と呼ぶもの、それは、私が世界はかくかくである、世界はこうあらねばならないと予め思い込み、そうきめこんでいる像のことなのではないだろうか。この、私によってア・プリオリに捕獲された〈イメージ〉は具体的には私による世界の潤色、情緒化となってあらわれるものではないだろうか。つまり世界を、私がもつ漫然たる像の反映、〈私の欲望、私の確信の影〉と化し、世界そのものをあるがままあらわしめることを拒否する私の一方的な思い上がりであったのではなかろうかということなのである。(以上「なぜ、植物図鑑か」傍点引用者)」とたたみかける。『PROVOKE』期、「肉声」を希求したアレ・ブレの中平の写真に「〈詩〉」を感じ、以後、それが失われ、中平の言説が「〈詩〉」の喪失した「自らの写真に毒された意味づけ」をなしているだけなのではないかという投書者からの批判への回答の体裁で書かれた中平卓馬のこれらの言述に表明する意志は、葛藤を垣間見せながらも一貫している。それは、「世界と私とをつなぐ〈イメージ〉」、「〈私の欲望、私の確信の影〉」からの意味の付与の一切を拒絶することであり、ファインダーをのぞく瞳、シャッターにかかる指の「ア・プリオリに捕獲された〈イメージ〉」の介在を否定し、「事物の存在」「あるがまま」を写真はとらえろということだ。
『PROVOKE』創刊号で岡田隆彦はすでに、この位相に肉薄する位相を別の言葉でとらえていた。「集団と組織のもたらす偶発的なあつれき・闘争、ひるがえって悲惨な事件や災禍などなど、どのような境位においてであれ、当の人間がせつない心情で自身をいっぱいにしたとき、つまり(いまわたしが立てた仮説にしたがえば)なにものか特別な,ほとんど強迫観念的の受肉かたる影像(obsessive imageというべきか)の力に押し迫られて苦しくてならないようなとき、かれの意識の動きというものは、まず圧迫や苦痛からの開放へ向かい、融通無碍の、光きらめく絶対的現実を欲求する.(「見えない、せつない、翔びたい」傍点引用者)」と。その時「人間にとってもっとも豊潤な可能態のことである」「〈自由〉そのもののかたちをその人なりの仕方で(ほの暗い内部空間のなかで像が印現してゆくがごとくに)具象しようとしている」というのだ。註に「絶対的な倫理そのものでありうるような現実」と補足される「絶対的現実」という一語には、「心情の無規制なたゆたいは,あるとき美しい光のたゆたいであってもそれのみで終るなら、自然のうちに消耗されてゆくものにすぎない.樹0木や屋根の瓦や雲や熱カロリーのようにひたすらそのままの存在の美しさを開陳しているとしても、それらは,表現行為を選びそれに選ばれた者にとって,さらにいちだんと活力強化すべき性質の対象であるほかないのだ.(傍点引用者)」と叙述されあるよう、ふたつの過程が刻みこまれている。ひとつは、事物にたいし「制度化された意味」を排し、事物の「ひたすらそのままの存在」位相を知ること、そしてもうひとつは、そこから見出される「〈自由〉」「可能態」の具象化が、不可避であり、不可欠だということだ。『PROVOKE』期の中平は、後者に、その以降は、前者に、写真を生きる比重を一気にかたむけたとうつる。絶望にもふれただろう、極限的な「せつなさ」に苛まれて。だから、「制度的に整序された視覚(ラング)」を切開する「肉声」の選択を破棄してでも、「見るとは、みずからを一本の眼差しそのものと化すことによって、これまで見ていたと信じていたもの、その〈内容〉〈意味〉をほかならぬこの眼差しの上で崩壊させてゆくこと、そしてそれを通して私を突き崩し、同時に、私を無限に創造してゆくことではないか。」「「受容的」であることは世界に向かって私を開くこと、世界に私を晒すこと、そして進んで私を解体させる勇気をもつということである。だがこの解体を通してしか私を再創造することもできないのだ。(「視線のつきる涯てⅠ」『決闘写真論』)」と言明されるように、事物と言葉、認識の結ばれと鬩ぎあいの位相に身を投じざるをえなくなったのだ。しかし、ここに記される「無限に創造」され、「再創造」される「私」という局面において、ふたたび「肉声」という問題が屹立する。中平の求める「私」は、「個性」や「自己」といった「近代の」「遠近法」に産出されるものではない。中平は、「間=主体(「個の解体・個性の超克Ⅰ」)」と言い、関係という位相を現実ととらえることで「〈私〉」から「〈世界〉」を変革する必要を説く。しかし、元来、中平卓馬の「肉声」を志した写真は、「人を震撼させる狂気に満ちた孤立した「物体」のような言葉」の体現をのぞんだと同時に、「関係」という現実のありったけを具体する生存、事物のすがたなのであり、「関係の関係」をどうフィルムに定着させるかを試行したとも述べられていた。はなから、中平の求めた「肉声」は、「近代の」「遠近法」に従属する「個性」や「自己」に還元される聲でも、発話でも、行為でもなかったのだ。『PROVOKE』期の「肉声」写真が衝迫した「関係」の倫理は、「植物図鑑」以後も、死んでいない。「私と他者の対話、私と世界の対話、そのせめぎ合いの中で「私」は関係としていま、ここに、在る。(「個の解体・個性の超克Ⅱ」傍点原文)」と。わたしは今、中平卓馬の見定めた局面に、倉重光則の掌、光を摑み、事物を摑み、こすり、ふれつづけるその掌をうつしこみたい。
一九六八年からの半世紀にも及ぼうとする四十幾年、倉重光則は、光をいかに経験し、倉重によって晒された光は何を経験したのか。『倉重光則個展July9-21,2012(ギャラリー現)』で倉重光則は、絵画を出品した。蛍光灯を配置されたものもあったが、多くは、絵画だけの展覧会だった。四〇年ぶりに絵を描いた、その間、描くことができなかった、個展の最終日、倉重はわたしにそう告げ、掌を見詰めていた。絵を描くことのできなかった四〇年という年月は、その切断が、蛍光灯の光を見出した時との襲なりを示し、倉重はその途絶えの理由を自覚している。絵画を描くことを知った手では絵画を描くことはできない、絵を描くことを知った手を棄てる、そのこころみを様々な方法をもちい、この四〇年間つづけた、自身の手を、他者の手にするために、倉重はそう言い、線を引く、色をひろげるそのひとつひとつの行為が「地下の闘争」だとつづけた。四〇年ぶりに絵画を描く行為は、「地下の闘争」なのだと。この四〇年間の全ての過程こそが、「地下の闘争」だったろう、わたしはそうとらえ直していた。「地下の闘争」、その「地下」の様相を倉重は、「地下で生存する生きもの、それと同時に出現する地下空間、その存在は重く皮膚にまとわりつく、地下=空間という思考が生まれる。そこでは眼は必要としない感覚の世界、目によって計測不能、見ることの不可能性としての存在。奇妙な永遠性と濃密な沈黙の世界。(「真青な風景」傍点引用者)」と自身で記している。「地下」はただ、定位としてひろがる場ではないのだ。「地下」はそこを生きるものが存在してはじめて出現する位相だ。つまり関係の位相だ。事物との距離と、その関係を生き、だからこそ、自らの身体と肉体と肉が、同一面上での鬩ぎあう位相だ。それは事物を可覚の直前の出来事に漸近しつづける。われわれは、事物を事物のままに感受することはできない。制度に組織された既成の文法、身体の構造は、われわれの事物との関係を統御し、規制しているが、それなしには認識、行為そのものが成立しない。視覚、聴覚、味覚、触覚を可覚する全ての器官は、体系に組みこまれている。それは当然、絵画においても同じだ。一すじの線を引くこと、縁取ること、色を選択し、塗ること、それらはある種の統御、規制のもとにはたされている。絵の描き方をしてしまっているというのは、既成の構造に支配されていることの実感の別謂いだ。しかし、それだけではない。そこで終わりではない。「〈内容〉〈意味〉をほかならぬこの眼差しの上で崩壊させてゆくこと、そしてそれを通して私を突き崩し、同時に、私を無限に創造」する余地は、絶えず確保されなければならないし、その余地は途絶えることなくひらかれつづけ、確認し直されつづけなければならない。構造はいつも、「未知の空間」を導入していなければならないのだ。それは、『PROVOKE』に宣言された「言葉にとっては裏側の世界」であり、倉重の言う「地下」であり、体系からの支配を掻い潜り、器官がおのおの独自を実存する位相だ。人間と非人間、イメージ、認識と事物そのもの、それらの区別のはざまに生じつづけ、蠢きつづける軋みそのものをなる位相だ。だからそれは「地下」と呼ばれるのだし、「地下」でありつづけなければならない。そこで「〈自由〉」、「可能態」を見極める。蛍光灯は、本来、その光を直接に見るのもではない。その光で、あたりを見せるものだ。光で見せるための機械であり、そう制御された光のはずだ。しかし、倉重は、光を見せることにより、別の「可能態」をひらき、光の制御の一端をといた。制御された光に封印された別の可能性の光を灯した。それはある意味で、われわれの身体に似ている。制御された光と共にとざされていたわれわれの身体の可能性をひらいたのだから。これは明かに、「地下の闘争」の途絶えぬ過程に顕現した、器官なき光、実存の光、光の実存だ。倉重光則が「地下=空間」と言う時、彼は、ひたすらに事物、光と対峙し、ふれ、関係し、往還し、自らの生存を「地下」に引き摺り降ろしつづけるのだ。関係の渦中にとどまりつづけるのだ。ほかでもない、「地下で生存する生きもの」に自身がなり、「地下」を出現させるために。倉重の「生きもの」と題されたテクストには、「休むことなく生成しつづける“いま、ここ”の時空。いまだ何も形成されず、非領域化されたもので、制限もなく、前提さえもしない。そこは運動と震動の世界。それらは私とは無関係に存続し、無関係に変化する非連続的な不確定性生物であり、発展生成である。/むしろそれは過程である。」つづけて、作品とは「脈打ちつづけ、生成し続ける生物である」「作品というよりは、いきもの」であると言及されている。一九七四年に遂げられた行為と時間のはかりがたき定着は、だから、その限定性を破るのだ。壁をこすりつづける掌の運動は、はたして、明かに現在に持続されている。その自覚があるからこそ、倉重は、自らの言葉、その組織を揺さぶり、攻撃し、「無限の創造」、絶え間ない「再創造」を要請することとなる。「安全という意味の名の下に姿を隠してきた物質たち 彼らはもはや正体を隠そうとはしない 死臭を発しながら姿を現し始めている 散乱する事物 意識と同時に 個々の名称は消え 突然 それそのものが現れる すべては欲動している 昼とも 夜ともなく 静かなブルーグレーの色彩に覆われた時空の中で 事物は事物であることを主張し始めた しかし生きているのは彼らだけではなかった 足の下でも 奇妙な地下の生命によってうち震えていた 錆びついた空缶 釘 泥に圧縮され朽ち果てつつある木片 根茎 極微動物 微生物や細菌や寄生虫は深みに隠れて活動してい。
彼らは火傷しそうな熱い液体を絶え間なく分泌し 垂れ流している いたるところに分泌腺があり 物質の奥深いところにも目には見えないが沸騰をつづける水ぶくれがあった 街路 壁 空 通行人の皮膚 それは本物の器官であり 奇妙な病気にかかって それぞれが勝手に体を震わせている生きた部分であった(「SCARECROW〈案山子〉」『層造』)」この文に著しい倉重の特徴的な記述は、「肉声」ではなく、「世界と私とをつなぐ〈イメージ〉」でもない。これらは、壁をこすりつづける掌が、事物に真向かいつづける全身が、その関係の渦中に生じつづける軋みの音、轟、出来事の経験に、言語を被せた、ぎりぎりの記録だ。その出来事、軋みの音のわきたつ位相を生存する人間と非人間のあわいからの報告、記録なのだ。八時間におよぶ壁と掌の関係に生じた正方形がそうであったように、倉重光則が、光と共に見せる事物のすがたは、「地下の闘争」の結果であり、「無限の」過程の具現にひとしい。倉重光則は、切り結ぶ。線は、面は、言葉を裂き、蔽い、圧し、潰すものを潰す、そのような行為としてある。生き方として。行為は、言葉を要請する。同時に、言葉が行為を要請する。ひとつの線、切り出されるひとつの輪郭、光自体の露出は、他者との邂逅に由り惹き起こされる自壊が、その関係のために組織をも共にはたさなければならないという祈りに漸近する意志の賭けだ。
ここでわたしはふたたび、『来たるべき言葉のために』の実践を想う。中平卓馬が、たとえアレ・ブレから「植物図鑑」へ写真に具体する形式の転換を迫られようとも、手放されなかった願い、意志、維持された倫理とは「来たるべき言葉のために」という言明に尽きる。そして、われわれは今、「能動」「受動」そして、「解体」と「再創造」を同律に引き受けうる言葉の具現を要請しているのだし、要請されているのだ。岡田隆彦は、「現実社会にたいする定見を放棄することは、虚構の構築を過不足なく行なうことと、基底部においてつながっていないのである(「見えない、せつない、翔びたい」傍点原文)」と述べることで、「解体」と「再創造」は「行為の過程で二者が複雑微妙に関わっている」が、その一方の成就が他方を一挙には、はたさないことを見破っていた。これこそが「絶対的な倫理そのものでありうるような現実」への必需だった。一方のみの加担では、致命的に足りないのだ。この見地は、今、一層烈しく、ひらいておかねばならないだろう。一方のみに加担する言説をもう信じることはできないほどに現在は、予断を赦されず、苦しく緊迫している。この苦しみを手放してはならない。耐えて、耐えて、耐えて、現在を可能なかぎり雪辱するために。この要請に終わりはない。それは「過程」でありつづけるのだから。今、ここまでを記し、六八年、岡田隆彦が、「見えない、せつない、翔びたい」とたたみかけ、発現した連語の願いが、倉重の、回顧としてではなく現在の意志、願いのすがたと襲なるを覚える。「言葉が、そしていまでは生成しつつある言葉の生を生きる言葉をうらづける(言葉の)組成・編成が、ものを光を世界を現在させる。そのことを幅広く地平にゆきわたる無名の感情と意識とが気づき知っているからこそ、言葉の自由なあらわれは、どのレヴェルどの場所どの次元においてであれ、ついに時代を未来に投企する最深の核である。(「生ける現在」傍点原文)」と岡田隆彦の記し刻んだ認識は、「言葉を生きる」ことで「生ける現在」の一切を見出してゆくことの決定的な姿勢をひらいている。『PROVOKE』そして、倉重光則の行為は、この言明を反転させながら同一の方位に運動を加速させてみせた。「ものを光を」現在させることで「生成しつつある言葉の生を生きる言葉をうらづける(言葉の)組成・編成」を要請し、うながしたのだ。それこそが「現実社会の構造的な歪みにたいする糾弾(「見えない、せつない、翔びたい」)」たりえると信じたのだろう。「制度的に整序された視覚(ラング)」への、身体、個を「整序」する「制度」への「切込み」は、一度いれて結実するものではなく、絶えず、PROVOKEしつづけなければならないものだ。憤慨させ、刺激し、挑発し、引き起こす動詞の姿勢とは別のすがたになったとしても、「過程」であることを自身に約束された行為と体現は、PROVOKEにならなければならない。つづけなければならない。だから、それは装置なのであり、「生きること自体」なのだ。一撃で終るものではないし、そうあってはならない。「地下の闘争」である思考と行為が終らない「過程」であり、自身の制作の具体を「作品」と呼称することをどこかで忌避しながら、「脈打ちつづけ、生成し続ける生物」「いきもの」と書き記した真意はここにあるのだろうし、倉重光則にとって、光を見せる体現は、制度を掻い潜り、回収を拒む時空間の把握「いま、ここ」を光源として晒していると言い換えてもいいのだ。それが地上に迫りながらも、「地下」であることにとどまりつづける運動であり、「言葉にとっては裏側の世界」からの、しかし、どこまでも言葉自身を渦中とする表裏一体の闘争だ。この表裏の鬩ぎあいにおいて、われわれは、絶えず、再組織、「再創造」する「可能態」、余地をひらき、提示しつづけなければならない。吉増剛造が、岡田隆彦、中平卓馬と同時代を生き、過ごし、およそ半世紀の時を経てなお、苛烈に言語、写真、映像による「肉声」の具体として他者の聲を託しながら、形式を創出しつづけている渾身の凄みは、ここにある。同様に、倉重光則の驚異的に持続する制作の具体もまた、光を見せる形式の具体的な創出に覚える。それらは、とめどなく「生成」されつづく。とめどなく、この言明は倫理だ。途切るな、途絶えるな、これは「絶対的な倫理」だ。
「「建築する(アーキテクテング)」ことによって、「新しい生命」の構築に向かいたいのです。できればプロセスをとおして、その国の法や制度も、変えていきたい(『生命の建築 荒川修作・藤井博巳対談集』以下同書)」と述べつづけたのは荒川修作だった。倉重光則が荒川修作の提唱した建築概念を自身の営為の一端にかかえこみ、応答の意志を胸に宿していたことは、奈義町現代美術館での本展覧会の開催が決まったと伝えられたとき、わたしはしった。荒川修作の「遍在の場・奈義の龍安寺・建築する身体」の空間を共に在ることは、歓びであり、闘いだと。倉重のこの告白にたいし、多くの補足はいらないはずだ。一九六〇年代初頭に単身渡米し、マドリン・ギンズと共に七〇年『意味のメカニズム』を発し、自身の主題を展開させてゆく荒川修作もまた、光を00生きる倉重光則、言葉を生きる岡田隆彦、写真を生きる中平卓馬とは別の方途で「過程」、「解体」と「再創造」の必需を実践しつづけた。つまり、身体で生きるのではなく、身体を生きること、それが荒川修作の到った倫理であり「死なないために」はその言明にほかならない。「「建築」は、身体の行為や運動を抜きにしては不可能です。」「歴史的なキュビズムの運動も、結局、視覚が中心となっていますから、まだまだ「精神」のためのものでした。だから、少し新しい概念は生まれましたが、身体の行為と、その環境との関係について学ぶということが、われわれのもっている言語ではいかに足りないかということを、二〇世紀はまざまざと証明してくれました。」の発言に顕著な、身体で生きるのではなく、身体を生きること、身体の変革から新たな人間、共同性を産出することを荒川修作は、可能なかぎり極論することでPROVOKEしつづけたのだ。その首尾に「国の法や制度も、変えていきたい」と言明している以上、それは新たな言葉、広義のテクストの要請にほかならない。
「(身体の)運動と足の裏(肉体)が同時に場を形成することが可能になる状態……。「建築する(アーキテクテング)」ことが生まれ始める……。」「「自分」の姿勢を不自由にさせてくれるもの、それが条件の一つです。姿勢が不自由になることによって、人は自分の「neighbor」知ることができる。自分の近所や環境との関係と、自分の五感の使用方法によって、呼びだされたり生まれてくるものがある。」「そして私が「建築する」と呼ぶものは、それに、前後・左右に「engaging bars(エンゲージング・バー)」「guiding bars(ガイディング・バー)」を必要に従い付け足していくことです。」これらの発言に籠められた荒川修作の意図は、中平卓馬が、徹底された事物の位相に自らを「受動」させ、「〈内容〉〈意味〉をほかならぬこの眼差しの上で崩壊させてゆくこと、そしてそれを通して私を突き崩し、同時に、私を無限に創造してゆく」必要を説いた言明と同義と見ていい。この「解体」と「再創造」の絶え間ない「過程」を身体に、明瞭なかたちで組み込み、自覚させることが荒川修作の真意だからだ。切り開く、ではなく「切り閉じる」と言い成したのは、この「過程」の所以だ。荒川は、それを身体の全身ではたすことに固執しているが、「私が身体の運動を必要としている理由は、新しい建築環境との交わりによって、まったく新しい感覚を呼び起こすためです。だから、まずプラトーと地形を変える、それが私の「建築」の決定的な条件なのです。主観の側からではなく、モノによって引き起こされ変えられる側ですね。(傍点引用者)」と述べられているように、その身体とは、やはり「関係」の倫理を体現するものだった。藤井博巳の「「表現」ということを捨てればよい。「表現」ではない。それを正確にいえる言葉を今は持ち合わせていないのですが、何か、機械や装置をつくることに近いこと……しか言えません。」との発言に対する荒川の同意は、彼の制作した「建築」が、身体で000生きるのではなく、身体を000生きる契機を発動させ、「関係」という現実そのものを根底から「構築し直す」「装置」であることを示している。つまり、「コモンセンス」を「構築し直す」ための「装置」だ。「「建築」の概念に、いつも「新しい共同性」としての意味を付け加えるようにせねばなりません。しかし、この透明度を切り刻んでいって、完全に不透明にせずにどこまで切り刻んでいけるか。このプロセスによっていろいろな関係が生まれ、それらの関係から生まれた現象は、きっと思いもかけない場所を生み出すことでしょう。」との言述は、その明瞭な表明だ。そのための基地位相となるのが「まだ「場」を持つことができず、「所」のような「振動しつつある環境」「呼吸している環境」」と呼ばれ、これは倉重の「地下」に、おおよそ相当する。「言葉にとっては裏側の世界」に対応するのだ。その地平での「「動きそのもの」と、その前景、後景との関係」である「空白の運動」と荒川が名指す営為は、まさに、七四年、田村画廊で倉重が壁面を撫で、こすりつづける掌を呼び起こすだろう。「建築的次元(ディメンション)の降り立つ場」として、「この足の裏の位置によって、毎秒ごとにとてつもないことが起こり、形成されている」ことを倉重の掌は、確認しつづけているとも言えるのだから。「生命を建築の形式を使って構築するということは、私が私自身の場を持たないけれど、外在としての「生命」をもつことも可能だ、ということなんです。身体の行為と外部にある建築的環境から生みだされた出来事と現象によって、「遍在の場」すら薄められ、場所を消失させる」と述べる荒川修作もまた、「近代の」「遠近法」に産出された「個性」や「自己」、それらに制御され、規制された身体の在りようを破ろうとしたのだ。「外部」に、言い換えれば関係として「生命」を「遍在」させる「装置」を「建築」することによって。徹底される関係が、全面化し、全景化した時、場所は消失するのだと。建築法規等に拘束されずに制作された「奈義の龍安寺」は、荒川修作の意志、意図を最も具体した「装置」だろう。それは、「これほどむちゃくちゃになってしまった世界」を変革するために「建築」されたのだ。PROVOKEするために。「新しい共同性」を獲得しつづけるために。
中平卓馬は、「世界と私とをつなぐ〈イメージ〉」を「世界そのものをあるがままあらわしめることを拒否する私の一方的な思い上がり」だと記し、「その〈内容〉〈意味〉をほかならぬこの眼差しの上で崩壊させてゆくこと、そしてそれを通して私を突き崩し、同時に、私を無限に創造してゆく」必要を説いた。わたしは、今、これらに記述されている「世界」をそのままに世界と受け取ることはできない。ある条件を要しなければならないが、その視線を「思い上がり」だともおもわない。ここで、中平の記す「世界」とは、「あるがまま」の「事物」の位相地平だ。世界とは、その地平と「私」(個々の生)を繋ぐ構造、制度であり、同時にそれを産出するものだ。いうなれば「〈イメージ〉」に相当し、関与する装置だ。そして、世界は今、「関係」の倫理そのものを圧殺しつづけている。関係を生きることで邂逅する他者、事物に、生存に、命に、切に真向きあうとき、現在、世界に散見される地獄から眼を、身体を、言葉をそむけることなどできない。われわれの闘争は、事物に対してではなく、世界に対してはたされなければならない。光を生きること、写真を生きること、身体を生きること、言葉を生きること、これらの渾身の営為は、事物との闘争をなど告げてはいない。世界に、だ。現実だ。それらで生きることと、それらを「生きること自体」とすることの差異、距離、径庭、隔絶を覚悟せず、自覚さえせず、無化するものに、現在を生きることなどできない。
今、われわれは、いかなる関係の様相を呈示すべきなのか。この問いの中で、倉重光則が、自身の行為、制作に生じる具体を「いきもの」と呼び示した誠実は、何度でも確かめ直さなければならないだろう。一九七四年の田村画廊での一連の出来事がそうであるように、この呼称は、倉重光則の生存の位置の誠実、切実を伝えてやまない。倉重光則が掌をすり減らしながら、しかし何も喪失することなく、壁をひたすらにこすりつづけた時間には、本来、終わりなどないのだ。一度、握手をかわせばわすれることができない倉重光則のおおきく厚い掌は、生存の生涯に懸けられた営為の具体そのものだった。その掌は確かに「いきもの」を護ろうとしている。その掌もまた、「いきもの」だ。「いきもの」を命と言い換えてもいい。それは紛うことなき命だ。
現在、われわれを蔽う世界は、この「いきもの」を封殺しつづけている。「言葉にとっては裏側の世界」「地下」なる位相も、さらには、「いきもの」、なによりも具体的な命を命として関係する視座をさえ封殺している。排斥する。世界との闘争だ。「いきもの」、命の具体、その生死、その彼岸、他者を圧殺する機構を強化しつづける世界に対して否を叩きつけ、PROVOKEするのだ。それらを護り、維持する視座と、存在の具体を奪還し、世界に遍在させるために。荒川修作が「生命の建築」を訴えつづけた言明は、正鵠を射ている。意味は、明かなのだ。われわれが関係という絶対的な位相に奪還し、生存の組織として普請しなければならないのは、命なのだ。「どのレヴェルどの場所どの次元においてであれ、ついに時代を未来に投企する最深の核」であると岡田隆彦が書き刻んだ「生成しつつある言葉の生を生きる言葉をうらづける(言葉の)組成・編成」を懸命に創出しつづけて。光を生きるから、写真を、身体を、言葉を生きるからこそ邂逅する一切に、現実の実景の逐一を見出してゆく。そして、光を生き、写真を生き、身体を生き、言葉を生きてはじめて、それらで生きるのではなく、光が、写真が、身体が、言葉が生き、それらで生かすという局面が、真に生じ、顕現するだろう。関係だ。命とは、紛うことなき関係だ。
本文の冒頭に引いた詩語は、いつも心の片隅にひらけてあり、鼓舞される、大切な詩集の言葉だ。その「死ねない光」は、確実に、倉重光則の営為に共鳴しておもえた。共光、そんな言葉を造ってもいい。そして、叶うならば、それらが響き、光り、鼓動する位置に、詩を寄せて、終ることはないだろう応答のひとつをはたしたい。
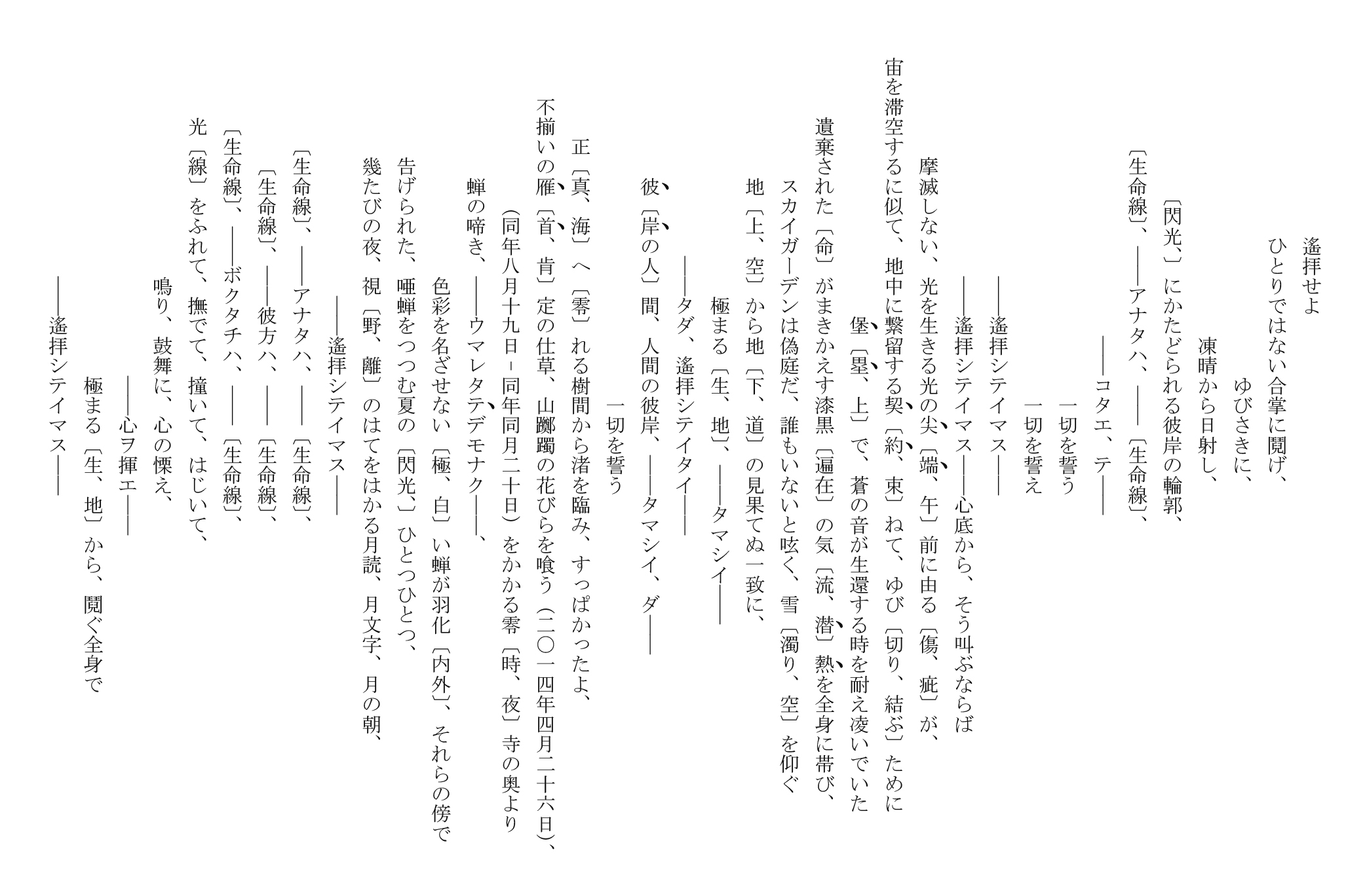
☞ 菊井崇史氏の文章には、多数のルビやふりがながあります。web上で表現が難しいのでルビはやむをえず省略し、ふりがなは、(かっこ)付きで付随しました。作者の意図が十分に伝えられない部分がございましことをお詫び申し上げます。

◼ 発光体(後部) 2002年 2003年 244x244x610cm. 鉄、蛍光灯 C・スクエア/神奈川県民ホールギャラリー