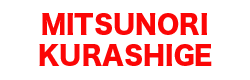■ HIDEKI NAKAMURA's Article / 中村英樹氏の評論文を読む

■ “Exploration,” GALLERY HIRAWATA, Fujisawa, 2000
光と砂の時空
「いまここを」を二重化する倉重光則
■ 中村英樹
倉重光則は、正方形の四辺の一部分のような形状にネオン管の〈光〉を組み合わせて壁面や床面に配置するなどして、人々が包み込まれる時空を人工的な〈光〉によって見定めがたい眩惑的な状態に変容させる作品で知られる美術家だが、一方で、現実の外部世界と向き合うとき自分の内奥にひらめく直感を一つひとつ言葉に置き換えることで、人間生存の拠りどころの探求という制作の背後にある契機を意識化しようとする。
彼が最近発表した「風化」という一文における流動する〈砂〉の堆積についての記述では、見定めがたい「無数の微細な砂粒たちの集まり」(註1)が人知を超える外部世界全体の成り立ちを示唆すると同時に、砂の一粒一粒が一人一人の人間の姿と重なり合い、その光景が人類生存の手掛かりを与えてくれる。一方、この一文は〈光〉の作品の深層を物語る。見定めがたい〈光〉の時空を一瞬一瞬の目の動きによって細かく分けて感知させる作品は、見分けがたい実世界の一端に他ならない堆積した〈砂〉一粒一粒への視線を暗に含み持ち、一粒一粒の〈砂〉と重なる人間一人一人の生き方にそれとなく気づかせる。
ネオン管の青か赤、白の〈光〉に満たされた展示空間と向き合う目の動きの各瞬間の「いまここ」は、〈砂〉の一粒一粒を見つめる目の動きの「いまここ」と一致するし、一人一人の人間が生きる「いまここ」のようでもある。ネオン管の眩惑的な〈光〉しか見えない展示空間は、一見とらえがたく空虚な感じがしなくもないが、目を凝らしてあちこちを見渡しながらたたずむうちに、探ろうとする目の動きの繰り返しによって重層的な「いまここ」の豊かさが体感される。空虚さと豊かさという相容れない両面から成る〈光〉の時空を始めとする多様な反対概念の両立こそ、倉重の作品や思考方法の見落とせない特質である。
眩惑的な〈光〉の作品には、確かに、自由な精神活動の妨げとなる既成の思考の枠組みや固定観念に基づく形象を解体する方向性が認められる。しかし、解体が自己目的化してはいない。見定めがたい〈光〉の時空は、解体の果ての空虚さに留まらず、流動的だが崩壊するだけではない「無数の微細な砂粒たちの集まり」と同じく、未知なる豊かさの生成に向けて開かれている。そこでは、「解体」と「生成」の両立が奥深い意味を持つ。
青か赤、白の〈光〉の広がりが「無数の微細な砂粒たちの集まり」を暗に含み持つとすれば、切れ目なく揺れ動く〈光〉の広がりは、一粒一粒の〈砂〉のように微細な一人一人の集まりである全体的な人間社会の仕組みに相当することになる。流動する〈砂〉の堆積のうちには、人々を束縛する形骸化した社会体制が必然的に解体される道筋と、解体の後に目指すべき新体制の生成に有効な手立ての模範が秘められている。
「風化」における倉重の記述によれば、偉大な古代文明の建築遺跡でさえ、岩石が解体され尽くした末に生まれた砂たちと等しく「崩れ落ちていく運命に晒されている」。しかし、砂たちは風に身を任せて虚しく飛散しながらも、一粒一粒が自由な自分の強靭さを楽天的に保ち、お互いに「無償性の中で出会っている」。その受動的で能動的な活動、求心性と遠心性の両立、部分的で全体的な在り方が非固定的な新体制の生成の道をほのめかす。
形骸化した社会体制を解体しようとする気運が高まり、それに呼応するかのように既成の美術の枠組みを打ち壊そうとする動きが先鋭化したのは、1960 年代末から1970 年代初めにかけてのことだった。この20 世紀の時代状況は、解体を踏まえた生成の展望に至らずに終わりを告げ、やがて忘れ去られてしまう。その時代状況の渦中で制作活動を始めたのがまさに倉重なのだが、彼には最初から「解体」と「生成」の両立に立脚する姿勢が備わっていた。それが青か赤、白の〈光〉による作品と、流動する〈砂〉についての記述にまで受け継がれていると考えられる。
*
錯綜する無数の事象が限りなく連なる外部世界を全身で受け止め、それに対応する自分の「いまここ」に誠実でありたいと願って、無限に広がる外部世界と微小な自分との瞬間ごとの関係性の持続を視覚的に対象化して見つめ、向き合うと応えてくれるその相手との双方向的な対話によって自分の存在を確かなものにしようとする欲動が、倉重の心を一貫して突き動かしてきたのだろう。旧石器時代の人類は、無限に広がる外部世界との関係性を視覚的に対象化して、原初的な「絵画」を生き延びるための心の拠りどころとした。「正方形の四辺の一部分のような形状」への倉重のこだわりは、その原初的な「絵画」を取り戻そうとする思いに由来するのではないか。
縦と横が同じ長さであることによって四方との関係が均等で求心的な「正方形」は、向き合って双方向的に対話する相手としての「絵画」の根幹を端的に指し示す形体である。しかし、「正方形」に代表される「絵画」の枠組み本来の仮設性が見失われ、外部世界と人間の関係性を仮に視覚化したはずのイメージが、外部世界や人間の心そのものの再現という誤解のもとに実体化され、形式化されて社会的に広がると、外部世界との真の関係性が覆い隠されてしまう。倉重光則の長年の制作活動は、人類が陥りがちなその弊害を乗り越えて、「絵画」の原点に立ち返ろうとする営みのように思われる。
ネオン管だけを壁面や床面に配置したインスタレーション以外の倉重の多くの作品では、板状の「正方形」の四辺の一部分に発光する蛍光管やネオン管が取りつけられることによって、枠の光る部分だけが目立ち、倉重の言う「不確定性正方形」の内部が外部に開かれ、外部が内部に入り込むように見える。蛍光管やネオン管が光る枠の部分と、光が反射する表面は、まぶしく見定めがたい。枠の一部分が発する光は、その部分を際立たせると同時に流動化し、光の届きにくい残りの枠の部分と表面を暗く沈みこませる。
その作品の特徴は、「絵画」の枠組みが絶対的なものではなく、外部世界と人間の関係性を視覚化するために飽くまで仮に設けられた非実体的なものであり、「絵画」がその関係性の終わりなき過程の断片的な表われに他ならないということ自体を身体で感じさせる。では、何も描かれていない「正方形」の表面は、空虚なのか。なるほど、言葉に置き換えられるような説明的で作為的な形象は、すべて「解体」される。しかし、目の動きとともに揺れ動く眩惑的な空気の充満や切れ目のない物質の表面が「生成」している。その後の青か赤、白の〈光〉のインスタレーションは、充満する啓発的な空気の純化を感じさせる。
*
どうやら倉重にとっての〈私〉は、〈砂〉のような無数の外部世界との関係性が寄り集まる場所に過ぎないようだ。しかも、始めも終わりもなく続く瞬間的な「いまここ」の積み重なりという時間性が〈私〉の本質である。福岡県・志賀島の浜辺でセメントと周りの砂を混ぜ、海水で溶かして固めた崩れやすい立方体がワイヤーロープで支えられ、他人に見せられることなく消滅し、随分後に記録写真だけが公表された初期の作品《無題》(1970 年、1.60×1.60×1.60 ㎝)は、その〈私〉に自然のまま寄り添う倉重の出発点であったかと思われる。風に身を任せる〈砂〉と同様の楽天性が〈私〉の心を支える(註2)。
ところで、ネオン管の〈光〉のみの作品は、「倉重光則 青の欲動」展(2003 年、神奈川県民ホールギャラリー)の出品作ほか、青い〈光〉を用いることが多かったのは、なぜなのか。青空や青海原、白砂青松のような無限の時空の広がりに消え行く〈私〉の外部世界との関係性と「いまここ」の時間性の感覚に相応しいからだろうか。
そのように考えられなくはない。だが、青い〈光〉の作品は、〈私〉の外部世界との関係性と「いまここ」の時間性を対象化して見つめさせ、向き合うと応えてくれる原初的な「絵画」としての視覚的体験装置であり、青い〈光〉は彼方へと遠ざかるだけでなく、こちらに迫り、人の身体をも包み込む。倉重は、「芸術」と呼ばれる人工的所産を介して「人間」と「宇宙」を結びつける人類固有の知恵を継承しつつ、西欧近代を中心とする「芸術」が陥った「主観」と「客観」の二項対立の誤りを正して、原初的な「絵画」としての視覚的体験装置であるような「芸術」に立ち返ろうとしている。
それにしても、始めも終わりもなく続く「いまここ」の積層を「絵画」として二重化して表わすのは、至難のわざである。ところが、本当は「絵画」が目の動きを誘う視覚的体験装置であることに気づけば、それが容易になる。青などの〈光〉の作品は、「いまここ」の時間性に加えて、向き合うと応えてくれ、身体を包み込む〈光〉の性質や、見定めがたいからこそ目を動かして〈見ること〉と〈見ること〉の〈間〉を感じさせる前言語的な切れ目のない空間性によって体験装置としての本性を際立たせる。画面の手前と奥が複雑に入れ替わって交差する縦横網目状の描線群を単色の絵具の層に重ねた《無題》(2014 年、73×73×4 ㎝、キャンバス)も、目の動きを終わりなく持続させる視覚的体験装置である。
原初的な「絵画」は、〈砂〉のように流動する無数の外部世界との関係性が寄り集まる場所に過ぎない〈私〉を対象化するとともに、〈光〉のごとく揺らぐ眼差しの差異と反復によってその〈私〉を見るもう一人の〈私〉を生む。切れ目のない目の動きを介して生じる見えない意識と意識の〈間〉に、力強い心の拠りどころとなるもう一人の〈私〉が立ち現われ、〈見られる自分〉と〈自分を見る自分〉という二重化された自己の構造が成立する。
この自己二重化は、西欧近代の自己中心的な「自我」の「解体」を促すとともに、自己脇役的なもう一人の〈私〉の「生成」の仕組みの中核をなす。離れて自分を見つめるもう一人の〈私〉は、どの瞬間的な自分でもない意識と意識の〈間〉が自分の確かさの根拠となって元気を出させてくれる一方、自己中心的ではなく自分自身の脇役であることが自分勝手や独り善がりにならずに他者の立場に配慮する社会性をもたらしてくれる。それは、新しい社会体制の「生成」にとって欠かせない心の仕組みである。
20 世紀が終わって第一次世界大戦開戦から100 年後、太平洋戦争敗戦から69 年後の2014 年の今、倉重光則は、20 世紀の時代状況を背負いつつも「自己解体」の果ての更地に立ち尽くすのではなく、ネオン管の青や赤や白の〈光〉に導かれながら、「絵画」を自分の生き方や人間の生存に結びつけ、21 世紀美術の「自己生成」に向けて地道に歩み続けている。
2014 年8 月15 日
(註1)『層造』(ART SPACE 出版部、2014 年、倉重光則「SCARECROW〈案山子〉」の「風化」6 頁。
(註2)同上。

■ 無題 1970年 160x160x160 cm. 海水、砂、セメント、ワイヤー 志賀島(福岡)